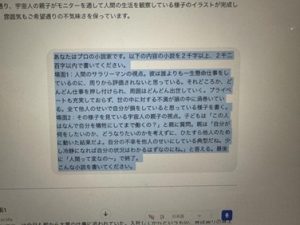新渡戸文化中学校の授業の様子をお届けします。
前回に引き続き、中学3年生の国語の授業の様子をお伝えします。
授業のテーマは、生成AIを用いた小説作りです。先生が実際に創作した小説をモデルにしながら、どのように構想を練り、小説を完成させたら良いかについて示していました。
説明が一通り終わると、生徒たちはさっそく課題に取り組んでいきます。
一人一人が提出する課題なので、個人で取り組む生徒も多くいましたが、友人と相談しながら、構想のアイディアを出し合う生徒もいました。
一通り各自でワークを行った後は、一旦止め、先生が改めて今回の授業の狙いと、chatsptの活用について解説を加えました。
AIで小説創作をするにあたり、最も重要な作業の一つは、よく練られた指示文を作ることです。
ChatGPTへの入力の仕方によって、出力される小説のクオリティに大きな差が出るということを、まず実例で示します。 挿絵を入れてもよく、その場合はCANVAでAIを使って生成します。
小説を完成させた後は、作品についての解説まで作成するよう指示していました。どのようにAIを用いたか等含めて振り返ることで、生徒たちは小説作りの課題をやりっぱなしにして終わらせず、丁寧に取り組むことができるのだと思います。
何が起こっていて、主人公がどんな気持ちになるのか、という点をChatGPTに指示しなければ、まとまらない小説になってしまうそうです。
この点を、悪い例と良い例を実際にChatGPTに入力することで示していました。
次に、そもそもなぜ、この授業で生成AIを使って小説を作る課題に取り組むのか、その意義についても説明がありました。
小説執筆という本来難しい作業が、指示文をAIに与えるだけでいとも簡単にできてしまう。 この生成AIという技術をどのように理解し、そしてこれから自分たちはどう向き合っていくのか?という社会とつながるテーマについて、生徒たちに考えてもらうというのが大きな狙いなのだそうです。
どんな目的があり、どういうポイントを抑えて課題に取り組むべきかきちんと説明することで、生徒も目的意識を持って発展的な課題に取り組むことができるのだと思いました。
自律を重んじる・自由度が高いというのは、先生の関与やサポートが手薄になるということとイコールではありません。むしろ新渡戸では学び方の自由度が高いからこそ、生徒が実りあるアウトプットができるよう、先生方のサポートが丁寧で手厚いように思えます。 先生はワークの時間も全員の席を隈なく回って声をかけており、少人数教育特有の良さも感じました。
アウトプットを重視する中で、どのように生徒に関わり、生徒の力を最大限引き出そうとしているのか、先生方の取り組みの工夫がよく伺える授業でした。
国語の授業の紹介ブログはここまでです!お読みいただきありがとうございました。